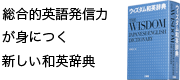まえがき
ことばは絶えず変化する.IT革命以来ここ10年,めまぐるしい国際情勢の変化の中で,特に英語の変化は著しい.国際化,グローバル化の流れに沿って,英語に World English(es) としての言語的展開など多数のバライアティを認めざるを得なくなってきており,それに応じて文法の規範性にも必然的に幅ができてきたといえる.
以上のような情勢を踏まえ,本辞典の編修にあたって留意した点は次の通りである.
1 authentic Japanese
本辞典の編修にあたっては,まず authentic Japanese を標榜した.これまでの和英辞典の用例は,先に英文ありきで,それを訳している傾向があった.つまり,英文の構造を伝えようとするあまり,直訳調のぎこちない日本語となっているものがいろいろと散見されていたのである.和英辞典は日本語から引く辞典である.その入口となる日本語がぎこちないのでは,その役割を十全に果たすことはできない.このような傾向を払拭し,自然な日本語を自然な英語に置き換えることの出来る和英辞典とすべく,以下のような工夫を行った.
(1) 国語辞典・日本語コーパスの徹底調査
最新の国語辞典を徹底調査し,慣用句・ことわざなどを大幅に取り入れた.また,各種日本語コーパスを活用し,日常的な表現の充実も図った.
(2) 日本語校閲
用例については,従来の英文校閲に加え,日本文についても専門家に校閲を依頼した.これにより,前述の「英文ありき」のぎこちない日本語を一掃し,自然な日本語の提示を徹底できたと考えている.
(3) 新語・カタカナ語の充実
最近現れてきた用語を積極的に取り入れた.(例: 居住空間 a living space / セブンイレブン直営店 a 7-eleven operated store [ 英
英 shop]) また,カタカナ語については,国立国語研究所「外来語」委員会編『外来語言い換え提案』なども取り入れ,充実を図った.特に和製英語については,その表記を
shop]) また,カタカナ語については,国立国語研究所「外来語」委員会編『外来語言い換え提案』なども取り入れ,充実を図った.特に和製英語については,その表記を 和製語
和製語 というレーベルを付けて示すことで注意を促した.
というレーベルを付けて示すことで注意を促した.
(4) 専門用語校閲
近年特に人気のある野球・サッカーの用語については,専門家に校閲を依頼し,日本語の直訳・説明的な訳ではない,生の英語を提示した.
2 ディスコース
本辞典では真に作文に必要な文章,つまりディスコースにも視点を置いた.従来の和英辞典は(単)文,つまりセンテンスが主であった.しかし,高校のライティング教科書にパラグラフライティングが導入されていることからもわかるように,現在の英作文はディスコース中心に移行している.このような流れを考えれば,和英辞典にもディスコースに関する情報を取り入れるのは当然のことといえよう.本辞典では以下のような工夫を行うことでディスコースに対応した.
(1) 談話文法の導入
ディスコース文を書くためには,そのための文法,すなわち談話文法の知識が必要になる.例えば,「私は数年間フランス語を習っていたが,パリでは私のフランス語が通じなかった」と言う場合,日本語につられて I had been learning French for several years, but in Paris I couldn't make myself understood. と副詞句を先頭に持ってきがちである.しかし,英語では I had been learning French for several years, but I couldn't make myself understood in Paris. と副詞句を後置する方が自然であり,文章のつながりがよくなるのである.本辞典の用例の執筆にあたっては,このような談話文法の概念を全面的に取り入れ,より自然な英語の提示を心がけた.
(2) レクシカルフレーズの重視
また,近年注目されるようになった「ツー」と言えば「カー」と無意識に反応して出てくるレクシカルフレーズ (lexical phrase) の表現の塊 (chunk) を身につけることも,自然な英文を発信するためには重要である.これらを構成する文には2つある.
(a) 会話の受け答え中の決まり文句: 「明日は10時にそちらに着きます」「着いたらお電話ください」 “I will be there at ten tomorrow.”“When you arrive, just give me a call.”
(b) 独立した単文で定型化したもの: 物分かりの悪い人だなあ Don’t you see what's happening? (=You don’t know anything about it. You are a fool.)
本辞典では,用例の随所にこのような表現を取り入れた.
(3) ディスコース文の解説
ディスコース文の用例をコラムとして掲載し,文の展開方法についての解説を加えた.ここで学んだディスコースの知識を活用することで,大学入試の自由英作文,さらには英語論文にも十分対応できると考えている.
3 日本人の心のふるさとを映し出す辞書
さらに,後世に長く愛用される辞書を目指し,読んで興味をそそり,人口に膾炙されている名言名句を用例として積極的に取り入れた.特に,古今の文学作品中に現れ,今に語り継がれることばについては,ディスコース文として掲載し,適宜解説を加えた.(例: 山路を登りながら,こう考えた.智に働けば角が立つ.情に棹させば流される.意地を通せば窮屈だ.とかくに人の世は住みにくい. 『草枕』) これらを通じて,単に英語を学ぶにとどまらず,日本人の心のふるさと,原風景をも感じていただきたい.それが日本文化発信の一助にもなると考えている.
『草枕』) これらを通じて,単に英語を学ぶにとどまらず,日本人の心のふるさと,原風景をも感じていただきたい.それが日本文化発信の一助にもなると考えている.
4 懇切丁寧な解説
本辞典のもう一つの大きな柱は,中級の高校生にも分かりやすい「懇切丁寧な解説」である.高校生が誤りやすい学習上のポイントについては煩を厭わず解説を加え,先生が生徒の英作文を添削する様を紙面上で再現しようとする試みは本辞典の姉妹書である『グランドセンチュリー和英辞典』でも行ってきたが,本辞典ではそれをさらに追求した.主な点は以下の通りである.
(1) 非文情報
「こうは言うがこうは言わない」,つまり日本人が誤りやすい項目についての記述を充実させた. (例) 教会で挙式の予定です Our wedding will be held in (×a) church. / 布地はメートルで切り売りする sell cloth by the [×a] meter
(2) 日英比較
日本語を直訳しただけでは意味にズレが生じるものについては,構文・文化両面から解説を加え,日本語と英語の発想の違いを意識し,より自然な英文を書くことが出来るようにした.
(3) 語法解説
語法の記述は詳しく扱った.記述の量の多いものは「解説」欄の囲み記事に,少ないものは煩を厭わず ( …) で注記した.特に基本語については随所に最大限の語法解説・注記を入れた.
…) で注記した.特に基本語については随所に最大限の語法解説・注記を入れた.
(4) 類語解説
英語は日本語と同様類語が非常に多い.そのため,語の選択が重要となる.本辞典では「使い分け」欄を設けて微妙なニュアンスを詳しく解説した.
(5) スピーチレベル
語の選択に際しては,類語のほかに言語的差異の問題がある.そのため 米
米
 英
英
 古
古
 書
書
 話
話
 俗
俗 などのレーベルを設けて,選んだ語がその使われる地域,社会,時代,文体に合っているかを確認できるようにした.
などのレーベルを設けて,選んだ語がその使われる地域,社会,時代,文体に合っているかを確認できるようにした.
(6) 連語関係
英文を作る際には語と語の繋がりを理解することが重要である.本辞典では,一つの語についてその前後,特に後にどんな語(句)が来るかを
 を用いて示した.
を用いて示した.
(7) PC関係
政治的に妥当な言葉遣い(PC: Political Correctness)も円滑なコミュニケーションには重要である.用例作成にあたっては,この点にも十分に配慮した.(例) 自宅通学の学生 a student commuting from his [her, his or her] home.
(8) 発音・音調
オーラルコミュニケーションを意識し,発音・アクセントを誤りやすい語句については,適宜発音記号・アクセント記号を付した.また,文強勢やリズムなどの音調についても,必要に応じて情報を盛り込んだ.
以上,本辞典を現代の英語の変化や語法研究の成果を全面的に取り入れた「本格的な語法文法の辞典」としての性格と,高校生にも分かりやすい解説を随所にちりばめた「懇切丁寧な辞典」としての性格を兼ね備えたものとすべく,スタッフ一同は編修作業に全身全霊を注いだ.Matthew Arnold の Essays in Criticism に記されている「世の中で知られ考えられた最善のものを学びとり,これを公正に後の世に伝える」義務が我々にはあると考えているからである.
本辞典の編修にあたっては別紙の編修委員,校閲協力者,執筆者の御世話になった.また,三省堂辞書出版部外国語辞書第一編集室の山口守編集長を始め,担当の金子真一,安藤まりかの両氏には何から何まで本当に御世話になった.心より御礼申し上げたい.
最後に,編者としては最善の情報を提供すべく本辞典を編修したが,思いがけぬ誤りや不備があるかと思う.今後さらなる工夫と改良に努力するつもりであるが,ご利用くださった方々のご叱正・ご助言をいただければ幸いである.
2006年(平成18年)夏
小西 友七
本書の編集にご協力いただいた先生方 (五十音順)
安藤 克典 飯塚 仁 生田 省三 砂金 紀 泉 政満 一法師克也
井出 清 伊藤 剛 伊藤 正一 稲垣 康和 稲葉 芳明 猪俣しのぶ
今井 茂 今井 康人 今田 祐之 今吉 正 宇都宮正朗 江藤 愉
遠藤 明緒 遠藤 満雄 大石 正昭 太田 亨 大村 雅三 岡本 裕子
岡本 泰 小川 心経 小栗 晶 長村 孝雄 小野 亮子 柿木 洋介
加藤 輝雄 加藤 雅仁 金子 章生 川島 智幸 川西 義広 菊池 徹
岸本 史雄 北尾 秀司 北堀 洋 草階 健樹 工藤 正宏 国重 徹
熊谷 祥生 黒川 佳子 毛谷 裕二 小泉 量裕 合田 和広 児島 敏郎
後藤 公英 後藤 隆之 木幡信一郎 小林 英治 小林 正美 根田 敬一
酒井 治 酒井 孝男 坂入 勝雄 坂田有士郎 佐藤 修一 佐藤 隆
佐藤 仁志 佐藤 昌功 三小田博昭 塩田 文昭 渋木 義夫 清水 晃
下田 和男 白井 宏明 杉浦 雅則 鈴木 聡 鈴木 晃彦 鈴木 寿秀
鈴木 雅範 瀬下 篤 髙城 真 髙田 恵子 髙田 幸司 高橋 哲徳
竹内 耕治 田中 慎一 田並 正 谷口 信一 谷口 雅英 谷口 正博
田村 達朗 田原真由美 千葉 圭 千葉 健司 積川 淳一 鶴田 欽也
手塚 達也 土肥 穣治 東方 誠 冨田 雅文 豊田 恵 苗代 直隆
長岡 秀一 中野 昭雄 長野 雅弘 中畑 義明 中林 義晴 中村 哲也
中村 弘之 永山 一夫 鍋田 和男 南條 敦史 西山 勝治 丹羽 和彦
布川 裕行 根岸 晃 野島 伸仁 橋見 誠一 畑 義則 原 博司
原子 彰 原田 和範 樋口 直人 平井 正朗 福﨑 穰司 福田 洋平
藤井 佳一 藤井 哲 藤井 良晴 藤田 鉄雄 藤田 正紀 藤塚 孝夫
伏原 一樹 二石 政彦 船戸 宙治 古川 陽一 本田 敦久 前田 美智
前原 義明 牧野 知美 益田 和之 町田 忠 松岡 正喜 松﨑 親男
松田 聡 松宮 晃 松本 秀樹 水迫 達郎 三谷 徳彦 道中 博司
宮本 洋一 宮本 順紀 宗里 佳子 村松 誠 森 孝志 森田 信彦
森脇 将成 柳生 敏克 安河内清徳 柳澤 真平 山岸 光男 山口 章
山下 敏伸 山田 道務 山野井康雄 山本光一郎 山森 義弘 淀縄 義男
脇山 哲夫
編修スタッフ
【編 修 委 員】 岸野 英治 三宅 胖
【校閲協力者】 石川慎一郎 (類語) 今野 真二 (日本文用例)
佐藤 尚孝 (野球用語) 曽我 邦子 (英文用例)
東本 貢司 (サッカー用語) Denise May Wright
【執 筆 者】 芦谷 民枝 池田久美子 石川慎一郎 石田 修治 大月みゆき
尾崎 恒夫 岸野 英治 香田 禮二 小西 友七 佐藤 隆
佐藤 尚孝 塩濱 久雄 曽我 邦子 月足亜由美 都築 郷実
中嶋 孝雄 中野 道雄 成田あゆみ 西田あおい 萩原 裕子
長谷川文代 東本 貢司 東森めぐみ 日比野克哉 三島 隆二
三宅 胖
【執筆協力者】 後藤 一章 坂本 智香 三木 望
【資料提供者】 有岡 佳子 石川慎一郎 磯野 市子 木澤 直子 中尾 桂子
装丁・見返し 岡本 健+
校正・資料作成 井内 長俊 小久保秀之 小松久美子 佐田 一郎 諏訪間 怜
三田百合子 山口 英則 文章工房・句読点
調査協力 日本アイアール株式会社
挿 絵 小林 和夫