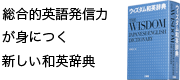ウィズダム和英辞典 小西友七先生追悼コラム
小西先生と三省堂 中嶋孝雄(元三省堂編集部)
忘れようにも忘れられないことの一つとして、三省堂の倒産がある。1974年のことであった。それに先立つ1968年に、佐々木達先生を主幹とする編集途上の「大英和」が中止になった。三省堂としても苦しい決断であったと思うが、この本の社側の唯一の担当者であった私は、上層部の決定に呆然とした。それでも、私は、再開がないわけではないだろうと一縷の望みを持っていたのである。それにしても、佐々木先生、佐野英一先生、木原研三先生、小西友七先生には、特に、申し訳ないという気持ちでいっぱいである。木原先生をのぞく三人の先生方は既に鬼籍に入られたが、人の生死を超えて、この辞書のことを思い出すごとに、私は、許しを乞いたい気持ちになるのだ。佐野先生は、当初全編を校閲するとの約束で仕事にかかられて、“この項別紙十枚に書き改める”の連続で、苦労に苦労を重ねられた。「もうしんどくてこれ以上は…」と、言われたのは、校閲が全体の四割弱終わったころと記憶している。小西先生は、特別執筆者として、機能語を含む重要語(われわれはこれを big words と言っていた)、計540語ばかりを校閲の手が入らない完璧さで書き上げられ、つづいて、類語解説欄の全部、1962年ごろからは、佐野先生を助ける校閲グループ陣の一グループを受け持たれ、誠実この上ない仕事ぶりであった。お二人ともに博士号がいくつか取れるほどの精力をこの「大英和」に注ぎ込まれたのではないか。
1982年、三省堂倒産から八年、『グローバル英和辞典』が校正段階に入ったとき、新しい学習和英辞典も欲しいという機運が高まって来ていた。山田和男先生の『クラウン和英辞典』が難しすぎるとの高校の先生方の声を学校訪問の営業部員が全国から持ち帰ってきていたのである。私は小西先生に頼むのが一番といい、もう一人の編集者は、別のすぐれた先生の名をあげていた。部長決裁で私の案が通り、私が下交渉をすることになった。善は急げで、広島へ春の辞書宣伝に行った帰りに、牡蠣を手みやげに神戸で途中下車した。「主人の大好物です」と奥様。お世辞かと思っていたら、「クワークほかの『現代英語の文法』―20世紀後半最大の英文法書―」(英語青年 1973年12月号)に Nothing agrees with me more than oysters, doesn't it? という文を引いて、この nothing を ‘local negative’ としているとの内容紹介をしておられるのはほかならぬ小西先生であるので、よほど気になる食品のようではある。この本については『慣用法』のことを書くときに改めてふれることにしたい。
ところで、私もかねがね和英辞典をもっと親切なものにしたいと思っていた。高校時代の私にとって、英語を書くのはパズルを解くようなものだった。まず第一に構文がよくわからない。辞書にある訳語のどれを使えばいいのかもわからない。わずかの例文から手探りで英語の文をひねり出す。そのような難行苦行を強いられたものだ。年をへて、大学入試の模試を採点するようになって、大多数の生徒はまったく英語が書けないこともよくわかった。
そこで、席につくなり、「先生、革命的な和英を作っていただけませんか」と単刀直入に切り出した。「そう、学校で先生が黒板に書いた生徒の英作文をいろいろ説明しながら添削されるようなものをね。革命的というより革新的なものね。おもしろそうだ。やりますか」ものの二、三分で「やる」という確約を得たのである。「中嶋さん、やりますけど、途中でやめるのは困る。何があっても本にすると約束してくれますか」。「大英和」で飲まされた苦汁は二度と飲ますな、とのきついお達しである。
神戸から帰って三か月ほどたった。先生からはナシのつぶてである。電話をすると「大学が忙しくて」とのこと。そのころ先生は図書館長、大学移転委員をされていて、本当にお忙しそうだった。「夏休みまで待ちます。辞書の構想をお示しいただければ…」等々話して電話を切った。その電話の直後、先生はバタンと倒れられたのだ。メニエル病、この病いが、後々長期にわたって先生を悩ますことになるのである。大学も休職された。病気の治療に専念されている間にも、簡潔なご指示はいただいていた。
- (1) 語彙は一万数千に絞る。
- (2) 基礎語に手厚いスペース配分を行なう。
- (3) 類語・縁語をグループ分けして原稿を書くようにする。
それを実際に整える仕事は三省堂ですることになった。
(1)の見出し語と基礎語の選定はベテランの高校の先生に依頼した。(1)が決まるとそれを表にし、四種の類書が各見出し語に与えている行数を調べ、基礎語二千八百については、類書平均の二倍のスペースを与えるなど思い切ったことをした。(3)の類語・縁語のグループ化は国研の『分類語彙表』によったが、思いのほか難事業となった。執筆開始後もこの作業は同僚の井内長俊さんによってつづけられた。
社は用例カードも提供した。三万五千枚の一般用例、一万二千枚の会話カード、八千枚の語法カード。これは釈迦に説法的であったが、そのころ、公刊されていた日本語による語法書が取り上げていた、ほとんどすべての項目をカード化したものであった。一々諸本に当たる手間が省けるようにしたものである。ただ、カード作成に時間がかかり、実際に活用されたのは、初校の校正においてであった。
ようやく第一回の編集会議が開かれることになった。この席で私は社の希望を話し、小西先生が、類語の扱いについて講義をされたが、私にはよくはわからなかった。小西先生のお話はいつもああいう調子なんですよ、と私の理解力の弱さを慰めて下さった執筆者もおられたが、実際のところ、奥の深いお話なのである。まず手始めに、皆さんに各自の考えで原稿を書いてもらうことにした。用意した類語・縁語のグループカードを渡した。こうした過程をへて、小西先生が組版で数ページに渡る見本原稿を書いて下さった。このようにして、執筆の基準が明確になり、まもなく、岸野英治先生、三宅胖先生ほか、次々に大学の先生も投入されるようになった。岸野先生は京都大学で、三宅先生は神戸大学で、ともに英作文を講じておられた。私は、これで磐石の態勢が出来たと思った。岸野先生は執筆経験の浅い執筆者のためにしばしば会を開いて下さった。今、『ウィズダム英和辞典』の編者の一人である、井上永幸先生は基礎原稿の校閲の終わり近くに参加され、初校校正で辣腕を揮われることになる。小西先生はあまりの赤字の多さに驚き、早々と、再校で読むと言われた。初校の校正は長期に及んだ。ネイティブチェックは、当時ソニー英会話学校にお勤めの都築郷実先生の手をわずらわせた。都築先生が、ゲラとは別に自分で○×用の例文を作ったりして、チェックに携わっておられたことが印象に残っている。
ようやく組版上のまとめの段階、つまり、類語・縁語のグループで書かれたものを一気にアイウエオ順に並べ換える段階となった。コンピュータ組版でないとこういう方式はとれない。重複原稿の削除は意外と大変で、今ほどコンピュータ編集の技術も進んでいなかったから、この重複部分は、いくつも本になったときに残ってしまった。
付録部分の「基本文型表」は森昌一先生と、山岡憲史先生の共同執筆によっている。(後に、別の人の手も入ったが) 文型表示などで、担当の森先生は、小西先生に助けを求められたが、「自分で考えなさい」とにべもなく断わられた。ここに小西先生の学問に対する厳しさの一面がみられる。自信がつくまで勉強しなさいということだろう。中学時代の恩師から、「十学んで一教える」と教わったと、小西先生はおっしゃった。
いよいよ本となって、岸野先生の明快な内容説明があり、営業部も大いに頑張った。親しみやすい漫画さしえを多数入れたこと、ロングマン社の会話教本による会話ページも気に入られたのであろうか、三省堂出版の和英辞典としては、空前の初年度販売部数を記録した。(何部売れたかはヒミツ)
「先生、この辞書は何点ですか」とお尋ねしたら、「70点くらいかな」と辛口のコメントが返ってきた。「それでは、80点、90点にするように改訂にとりかかりたいものです」「やりましょう」 このようにして、第二版へ向けて私たちは、初版出版後間を置かずに、出発したのである。学校の先生間に、見出し語が足りないとの意見が支配的であったことも改訂を急いだもう一つの原因であった。
以上、『センチュリー和英辞典』の成立について、そのあらましをのべた。小西先生の力強い統率力があってはじめて、この辞典が生まれたのだと思う。また、この辞典編集に参加し、大きく飛躍された方々もおられる。小西先生は、人材育成という点でも、学問を次の代の人々に上手にバトンタッチされたという点でも、たぐいまれな方であったと思うのである。別の専門辞典の編集中にもご自宅の近くで、執筆者の方々とよく議論をされていたようである。「若い人といろいろ議論ができて、楽しいですよ」と目を輝かせておられた先生の温顔がまぶたに焼きついている。
まだ会社にいたころの話。目の前の書架に目障りな一冊の本があった。大塚高信編『英語慣用法辞典』(1961)である。やたらと部厚くかっこうが悪いのだ。今でいうメタボリックシンドローム的な本で、その脂肪分はいつか取り除きたいと思っていた。この本は大塚先生の説明によれば、『新英文法辞典』(1959)を作るとき、「語彙文法も加味したいと思って小西君に執筆を頼んだら、いっぱい書いてきて、たくさん余ってしまったんですよ。せっかく書いてもらったものを捨てるのももったいないから、別の人たちにも追加執筆してもらって本にしたんです」ということだった。そのうちに、『新英文法辞典 改訂版』(1970)が企画進行していたので、慣用法辞典もということになった。はっきりと憶えていないが1969年に大塚先生に改訂を依頼することになった。私が社側の窓口になった。私はただ一言「二百ページ減らして下さい」とお願いした。「よろしい。二百ページ減らすんだな。今回は小西君に頼みましょう。改訂版だから百万円でやってもらうように頼んでおきます」
1972年1月末、約束より一か月遅れで小西先生から速達はがきが届いた。「貨車便で新橋駅止めで原稿を送りました。お受け取り下さい」。超高層ビルが林立する新橋界隈しか知らない人はここに昔、鉄道の貨物駅があったと言ってもピンと来ないだろう。原稿はなぜか親切に会社まで配達された。ゲラになって驚いたのは、引用文の訳に誤りが目立ったことだった。当時課長だった鵜沢伸雄さん(後、上武大教授)と別々にゲラを見てチェックし、小西先生に送った。電話で「あの引用文はヘミングウェイの『老人と海』の冒頭近くにあるものですね」などと話すものだから、私はいつの間にか、大変な読書家だと、小西先生から言われるようになった。(これはウソ。たまたま知っていたので、私の悪いくせ、知ったかぶりが顔を出してしまっただけ)
ようやくページアップのところへ来て問題が生じた。というのは、Quirk et al のA Grammar of Contemporary English (1972) が出版された。Jespersen の MEG などと異なり、イギリス人自身が作った現代英語の文法書ということで、わが国に輸入される前から評判で、一早く紹介記事を雑誌に書いた人もいた。小西先生から東京で手に入らないかと言われ、書店に注文したのでは時間がかかるので、そのころよく訪れていたブリティッシュ・カウンシルに問い合わせたら、専用パウチで二、三日前に来たということであった。「大至急航空便で取り寄せるので、それが届くまで、貸していただけませんか」と厚顔無比なことを願い出たら、快く貸していただけた。その日の速達便で送ったところ、すぐに返事がきて、「南出(康世)君が全編を読んで、必要事項をゲラに反映させてくれるということになりました」ということであった。ここで南出先生の大奮闘が始まるのである。課長からは、出版時期を大幅に遅らせる気かと文句を言われたが、Quirk なしでは出版と同時に古い本になってしまうように私は感じた。
索引の作成のときには、小西先生の手元にはもう数万円しか編集費が残っていないことがわかったので、「大塚先生に話してもう少し出していただきましょうか」と言うと、小西先生は「何とかします」とだけ言われた。
Quirk et al の本の索引があまり役立たないことを知って、小西先生は索引はいいものを、と強く思われた。したがって、索引の作成者には厳しい注文をされた。二人の作成者にはいかほどの謝礼が支払われたのだろうか。
書名・編者表示は大塚先生のご意向で、小西先生との共編ということになった。小西先生は戦争後、京都大学で大塚先生から教えを受けられたが、「大塚先生の講義で、はじめて文法のことがよくわかるようになった」と私に話して下さったことがある。常に控えめで、誠実で、相手の立場に立って考えようとされる先生、大塚先生をしてこの分野で今や日本一だろうと言わしめた先生を、大塚先生が自分の著書の後継者として選ばれたのは自然の成り行きであった、と私は思うのである。このようにして、『英語慣用法辞典 改訂版』(1973) は出来上がった。
出版記念会で、大塚先生のスピーチについで、小西先生のお話があった。その中で、「ぼくらだけでやっていたら、とんでもない本を作ってしまうところだった」と、先の誤訳の件に言及されたのには驚いた。きっと、教え子の方々に、有名出版社から出た本に自分の名前が載ったからといって得意になるな、とさらなる奮起をうながされたものと、私は受け取ったが、私なら、教え子に恥をかかせるようなことは言わなかったと思う。そうは言うものの、小西先生ほど親身になって教え子を育成された人も少ないのではないか。南出先生が、『英語の辞書と辞書学』(1998)を出されたとき、小西先生は私に葉書を下さり、「南出君の本は読まれましたか。立派な本を出されて、わがことのようにうれしい」と言及されている。他の教え子の方々の活躍ぶりも目にし、その成長ぶりをうれしく思っておられたことはまちがいない。
1992年初夏のころ、荒木一雄・安井稔共編の『現代英文法辞典』が出版された。それ以前から、小西先生には時をみて、『英語慣用法辞典』の改訂版ということではなく、先生独自の『慣用法辞典』を作っていただきたいと三省堂から申し入れてあった。『現代英文法』は判型も大きく、千九百ページにも及ぶ大冊で、編者の配下の170名もの方々の参加を得て作られた。この本は同僚の井内さんが、独力で持ち前の粘り強さで完成させたのである。この本を手にして、考えられるところがあったのであろう、「うちは少数精鋭でやりたい」と言われ、八木克正先生ほか10名のお名前を言ってこられた。内お二人は岸野先生のご紹介で参加して下さったと記憶している。このころ、『センチュリー和英辞典』の初めての改訂が始まっていて、私はそのための用例集めにのめり込んでいたので、語法辞典の方の進行には十分な力が入らなかった。ただし、小西先生と相談して、今回は署名原稿にすることに決めたり、送られてきた項目リストを先生方に送り得意の項目を指定執筆していただく段取りはした。早く書いて下さった方もあったけれども大半は大学で役職につく年齢の方々であったし、また留学する方も出て、進行は大幅に遅れ、自分が執筆すると言われた項目も、時間的にむりだからという理由で、返してこられるものが多数に及び、進行は頓挫した。2000年には本にしたいとの小西先生の計画は崩れ去った。1996年春にこの辞典の編集会議を神戸で開き、井内さんに正式に受け継いでもらった。その後、この辞典の編集がどのように行なわれたかの証言は、井内さんにお願いするほかないが、一筋縄では行かなかったことは、これ以降完成まで十年の歳月と、三十名に及ぶ執筆者が次々に投入されたこと、出来上がった本の項目が最初選定された項目とかなり異なるところを見ると、明白である。
さて、完成された『現代英語語法辞典』(2006)を手に取ってみると、高齢の小西先生にとってこの仕事がいかに身を削るものであったかが、よくわかり、手を合わせる気持ちになる。コンピュータを駆使し、データベースを解析して考える今の語学のあり方に適合していく難しさを感じておられたのではないだろうか。とはいえ、Fowler 兄弟の編んだ POD を超える小辞典は今も出ていないし、Fowler, Modern English Usage (1926) を改訂した Burchfield 先生も、巨大なデータベースはそれほど使っていない。目利きの個人が集めた例文から帰納した学説は今も重きをなしていると思う。小西先生はそういう「目利き」で、公刊された多くの著作がそれを物語っている。コンピュータ一辺倒がよいとは限らないと私は思うけれども、コンピュータを駆使した興味ある論文も書かれている (S. Isozaki, A Study on the Suffix -ee in English: A Diachronic and Synchronic Approach (RANDOM No.30 2005))。
新しい『語法辞典』を拾い読みして34年前の『慣用法 改訂版』の執筆に参加された数名の方々の執筆項目を読ませていただいて、“ただ一生懸命に書いた”昔とは違う一流の風格を感じ取るのである。八木先生執筆の各項には時代の息吹きを、柏野健次先生執筆の各項には長年の研鑽の重層的な響きを、南出先生の lexical phrase には書くことを楽しむ学者の姿が見えるのである。その他の方々の執筆項目にも目を見張るものがある。類義語の記述はより明晰で、共起制限もよく調べられていて、前の版のそれより著しく改善されたということができると思う。中野道雄先生の Translation and usage や高増名代先生の Swearing は、お二人の著書のエッセンスが記されていて短いが重い。その他の方々の執筆項目にくわしく触れることはできないけれども、適材適所の方針は貫かれていてよいと思う。
小西先生はかつて、「いろいろ仕事をしてきたけれども、頼まれてした仕事がほとんどだった」と述懐されたことがある。三省堂のお仕事はみなそうであった。先生最後の業績となったこの辞典の中に、Basilect (in Black English) という項目がある。先生は、若いころからこの方面に注目し、研究を重ねてこられた。ある時、先生のお宅を辞するとき、「中嶋さん、帰りの電車のつれづれにこれでも」と言って手渡して下さったのが、「黒人英語の起源と脱クリオール化をめぐって」(1986)だった。びっしりとメモが書き込まれた Uncle Remus のテキストを、その時見せていただいた。アメリカ国務省の同時通訳官だった長井善見先生も南部方言、黒人英語にはひどく悩まされたと私に話してくださったことがある。小西先生はこの難物と取り組み、多くの論文を発表されてきたが、後につづく研究者のために、この Basilect という術語をぜひ解説しておきたいと思われたのであろう。
この稿を書いている間、ずっと小西先生と接してきた長い年月を振り返っていた。そうして、先生のことは、“よく身についた愛と奉仕”という言葉に収斂されると思うようになった。人間と学問に対する愛と、万事に対する奉仕の精神である。これらは一体化しており、論理や理論を超えて人生で最も必要で大切なものではないだろうか。小西先生のご冥福を改めてお祈り申し上げます。
(なかじま・たかお)